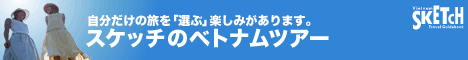<大いなる知恵、それは自然がもたらした。>
全ての素材は、庭先から

右)泥藍を長期保存する際、藍の色素が飛ばないように、栄養分として、時おりお酒を注ぐ必要があるという。そのため、彼らの中で藍は「酒飲みの男」と例えられる。
 |
 |
|
|
染め上げる布の量にもよるが、一つの樽につき約0.5kgの泥藍が使われる |
|
|
 |
|
|
|
藍液に麻布を浸けるのは約1時間。そして空気にさらし、また浸ける行程を、約3回くりかえす |
|
できあがった泥藍を水の張られた樽に溶き入れ、そこに発酵を促進させる米酒、色を鮮やかにすると共に藍の臭みを消すザボンやレモンなど数種類の木の葉を加える。そして、わらを燃やした灰から作った灰汁を注ぎ、更に7日間。毎日少しずつ泥藍を足し、十分に藍の濃度が高まった時、ようやく染めの準備が完了する。
準備だけで約2週間。なんとも気の遠くなる話だが、彼らにとっては当たり前の作業。シさんは、液に浸けた手織りの麻布を引き上げ、そして再び浸けることを繰り返す。
藍の色素は他の染料とは違い、色の定着に媒体を必要としない。藍が空気に触れることにより酸化し、自然に色が定着するのだ。とはいえ、もちろん彼女にそうした化学的な知識があるわけではないだろう。
だが、自然と共に生き、長年培ってきた経験から、彼女はその化学反応を利用しているというわけだ。
|