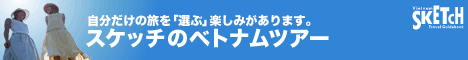琉球藍。類まれなる染めの至宝。
藍に咲く、濃紺の花

樽に咲いた藍の花。耳を澄ませば「サー」と、細かな気泡のはじける音が聞こえてくる。
 |
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
消石灰は、サパ近郊で採れる石灰岩を、約7日間焼き続けたもの。品質はザオ族が作るものが一番とされ、時おり開かれる地元の市場で、1kg5万ドン(約350円)で取引きされている |
|
|
|
 |
|
|
水を混ぜ、泡を立てる。間に自分の手を挟むことで、更に攪拌の効果を上げている。攪拌の時間はおおよそだが、水と泡が立てる音で、その頃合いがわかるという |
|
10人の子供を持つシ(Giang Thi Si)さん(50歳)は、村でも有数の藍染め職人のひとり。田植えと収穫で忙しい春と秋を除く季節は、毎年欠かすことなく藍染めを続けてきたという。
藍で染められた布は、その独特の香りが防虫の効果を持ち、消臭や保温の効果も高い。また染めを繰り返すにつれ、その色合いは赤みを帯びた紫紺に変わり、上品さすら伺える美しさとなる。しかし、その作業は一朝一夕にできるものではなく、季節、気温、湿度などに関する長年の経験がものをいう、まさに職人の世界。シさんの娘たちも藍染め自体はできるというが、上手くはいかず「いつも自分の仕事になってしまう」と彼女はこぼす。
藍染めは、まずその染料となる泥藍を作らなくてはならないが、実はその行程が最も大切。泥藍の良し悪しが、染め上がりの色を大きく左右するからだ。使う藍の木は1年ほど前に植えたもの。各家庭には専用の藍畑があり、泥藍を作る直前に刈り取るという。
モン族と同じく優れた藍染めの技術を持つタイ族の間では、藍の木には藍色を生み出す精霊が宿っていると信じられている。そして、昼間留守にするその精霊が、木に留まり眠っている朝夕の時間帯のみ、刈り取りを行うことができる。サパから車で約1時間のバンホー村に住む、藍染めの名人ウット(Lu Thi Ut)さん(48歳)が、そう言っていたのを思い出した。
刈り取られた葉を樽一杯に詰め、葉が浸るまでたっぷりの水を注ぎ込む。そして待つこと3日。藍の色素が溶け出し、緑色に染まった水の表面には、赤紫色の光沢を放つ薄い膜が張っていた。葉を水から引き揚げ、消石灰を溶き入れる。発酵し、酸性となった水がアルカリ性となることで、藍の色素が水と分離し、泥の形で沈殿するのだ。
すると、彼女は激しく水を攪拌し始めた。消石灰で白く濁った水は次第に青く変色し、水面にキメ細やかな泡がみるみるうちに立っていく。約20分ほど続けなければならないと言うが、それははた目にも大変な重労働。そして、まんべんなく消石灰が混ざったその時、樽の中には鮮やかな濃紺の泡「藍の花」が咲いていた。
|